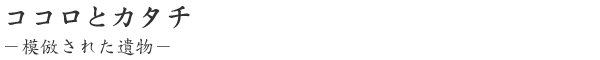No.317
考古・民俗展示室
平成20年4月8日(火)~6月15日(日)
 |
| 弥生時代前期の壷(後側)と中期の壷(前側) |
はじめに
土器や石器は時代や地域によって形が異なっています。それぞれの形態の違いを見るとその土器や石器を作った当時の人々の考えや思想基盤が見えることもあります。考古学とは、本来そのような遺物の形態から当時の社会を復元する学問です。
考古学の分析方法として一般的なものである「型式学」は、時代毎の遺物の形態の変化を比較検討する方法です。その理論の根底は、遺物の形態は前代の形式を踏襲、すなわち模倣しながら少しずつ変化するという前提に立ったものです。展示の前半では型式学の説明を軸として形態に対する分析方法を説明します。
さらに、考古遺物の形態にみられる地域的な違い、祭祀遺物の形態に見られる違いに注目してみます。出土資料には、他の遺物の形を真似したもの、もとの形をデフォルメしたもの、あるいは本来その用途として作られたものでないものを代用したりする例が少なからず見られます。特に祭祀に使用した遺物は実用品と比べて大きさや形態において大きな違いがあるものが多くなっています。このような、地域や使用背景による形態の違いを比較することで、製作・使用に伴う当時の人々の意志、認識や社会的背景に迫ってみましょう。
「型式学」とは
型式学とは、19世紀の後半にヨーロッパで生まれ、普及した研究法で、スウェーデンの研究者モンテリウスらによってまとめられたものです。この時に考えられた型式学は2つの前提に立ったものです。
一、人為物の「型式」は、動物や植物の「種」のようなものである。
二、生物の種が系統的に進化するように、人為物の型式も系統的に進化する。
このような考えは当時発表されて間もないダーウィンの進化論の影響を強く受けたものです。実際の資料を検討すると、この前提条件に沿った形で土器や石器の形態が変化することが確認できます。
例えば、北部九州の弥生時代の遺跡から出土する甕形土器は、縄文時代晩期から弥生時代後期まで少しずつ形を変えながら続き、その変化には明確な連続性が見られます。その変化はあたかも「土器が進化していく」ように見えます。実際には土器が子供を生むわけではありませんが、土器を作る人間が前の代の土器を模倣しながら代々替わっていくので、それが土器の形態に反映されているのです。
また、これも生物学的進化と同様に、「退化」という現象も見られます。これは当初は有機的な機能を持って使われていたものが、次第のその機能が使われなくなるにつれて形を変え、最後にはその部分が消失してしまうことを指します。
弥生時代の前期(紀元前5世紀~3世紀)に使われていた壺形土器には、表面に幾何学模様が描かれたものが多くみられます。この模様の中には短い平行線を斜めに3~5段重ねた「羽状文(うじょうもん)」と呼ばれる文様がありますが、この文様は古い時代には線がきれいに整い、横方向に線が入った極めて規格的な文様ですが、時代が下がると線が崩れ、文様自体が「退化」してしまいます。
また、古墳時代の須恵器に「提瓶(さげべ)」という器種があります。本来は紐を付けて吊り下げて使用するための輪が付いていましたが、次第に吊り下げて使用しなくなったと考えられ、輪の部分は鍵状になり、突起状に変化し、ボタン状に変形してついにはなくなってしまいます。実は鍵形に変形した段階ですでに吊り下げるという機能は失われており、その後は痕跡として単なる装飾が残っているにすぎません。この「痕跡器官」の考え方もまた、生物学の考えからきたものです。機能を失った時点ですぐに消失すべき部位が形を変えながら残存する現象は、物に対して私たちが持っている「カタチ」のイメージが強いために、すぐには違う形態を作ることができないことを意味しています。
 |
| 図1 古墳時代の提瓶の把手の変化(番号は展示番号に同じ) |
このような型式学の考えを利用して、遺物の形の変化を考えることができます。しかし、遺物の形の変化をたどる方法はそれだけではありません。発掘調査を通じて出土した遺物には出土した位置や、出土した層位が記録されています。この出土した層位の上下関係から、遺物の前後関係が分かることがあります。土層の堆積は、下が古く、上層が新しいことはよく知られています。つまり、「下の層から出た土器の形は古く、上の層の土器の形は新しい」ということになります。こうして下層から上層へ順に遺物を配列して遺物の組列を編むこともできます。このように遺物が出土する地層の堆積状況を検討することは層位学とも呼ばれています。
こうして器種ごとの遺物の組列ができあがりましたが、これだけでは十分ではありません。それぞれの時代にどのような遺物の組み合わせが存在したのか、その疑問はすなわち当時の社会を復元構成するために必要なものです。この疑問に答えるのが「一括遺物」です。これは住居跡や井戸などから出土した、明らかに同時に埋没したとみられる遺物のセットのことです。その組み合わせを見ると、ある時期にどのような遺物のセットが存在していたかを知ることができます。
このようにして私たちは、どの時代にどのような形の遺物が使われていたのかを知ることができます。そしてそれを考える時に、常に当時の人々がイメージしていた「カタチ」について思いをはせる必要があるのです。
ココロを表すカタチ
祭祀用の遺物は日常的に使用する遺物とは文様や形が異なることが多々あります。北部九州の弥生時代の丹塗磨研土器は表面に赤色顔料を塗布して磨いたもので、日常土器とは見た目が大きく異なります。この土器は主に祭祀や葬送に使用されたものと考えられています。このように祭祀に用いられたと考えられる遺物は、日常使用する同種の遺物とは形状や大きさが異なっている物が多いのです。
形状はそのままで大きさだけが異なった遺物もまた祭祀用に作られたと考えられています。大きさが5cm以下のミニチュア土器はその用途が実用的なものではなく、祭祀に用いられたと考えられ、日常土器の形を模したものもあります。
また弥生時代後半の鉄斧の形をそのまま縮小した形の「ミニ鉄斧」も博多遺跡群や南八幡遺跡群から出土しています。通常の鉄斧は幅5~10cmの大きさですが、このミニ鉄斧は幅1cm程度で、斧として使用することはほとんどできません。このような土器や鉄斧のミニチュアはその物が持っている「概念」や「存在感」を際だたせて表現することができるものと考えられます。
形を小さくするだけでなく、材質を変える(変えざるを得ない)こともあります。弥生時代の遺跡から出土する土製の勾玉は本来硬玉やヒスイで作られる事が多い勾玉の形状を土で真似たものです。また円板に鈕がついた土製品は鏡を模した物と考えられており、これらの土製の勾玉や鏡は本物が手に入りづらい状況下での代用品と考えられます。
子供の頃のままごと遊びもそうですが、祭祀や葬送の場にあるミニチュアやつくりものは、それを用いてあたかも本物と同じように演じることで行為自体を「概念」化してしまうための道具で、古代の人々はそのミニチュアやつくりものの「カタチ」に物の本質を当てはめていたようです。型式の変化もそうですが、「カタチ」に対する見方には私たちの「カタチを見るココロ」が反映されているのです。
(大塚紀宜)
(参考文献)
大塚初重ほか編『日本考古学を学ぶ(1)』1978
近藤義郎ほか編『岩波講座日本考古学1 研究の方法』1985
C.レンフルー他『考古学 理論・方法・実践』2007