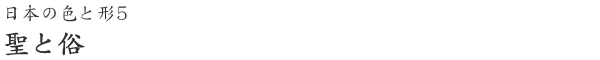No.227
黒田記念室
平成15年7月29日(火)~9月21日(日)
◆はじめに
戦国の世が終わりを告げた江戸時代初期、宮廷の秩序が回復するとともに中世以来の和歌や物語などの古典文学が復興、整備され、広く親しまれるようになります。それは当時の知識階層にとって憧憬すべき往古の典雅な世界でした。
一方で、室町時代の末期から起こった風俗画の発展でもわかるように、近世は現実世界に対する強い関心が美術の性格を大きく変えていく時代でもありました。
このふたつの流れが出会い、混交し、融合していく姿に、江戸時代の絵画の特色を読みとることができます。「日本の色と形」シリーズの第5回目であるこの展覧会では、相反するふたつの意識を「聖と俗」というキーワードにおきかえ、江戸絵画の奥深さとおもしろさを紹介いたします。
◆聖なる人物像の俗的表現
仏や聖人、また実存した人物であっても礼拝や尊崇の対象となる人物を描く絵画では、理想化されおごそかに荘厳された姿で描かれることが目的に合致した表現でした。しかし、そこに生々しさや写実性、人間味が感じられる表現が加わっている点が、かえって作品を魅力的なものにしている場合もあります。例えば住吉具慶が描いた「柿本人麿像」は、伝統的で型にはまった表現から逸脱し、誰か現実の人物をモデルにしたのではないかと思わせるような描写で、中世やまと絵の伝統から一歩進んだ新しい表現に対する意欲が感じられます。そこには、歌仙とはいえ生身の人間だったはずだという画家の強い意識が働いています。
◆美女の聖と俗
 6 文読む美人画 |
美人図といえば、江戸後期の歌麿などの浮世絵版画を思い出しますが、女性の美がひとつの主題として描き始められたのは17世紀のことです。最初は女性そのものよりも、華麗な衣装をまとった立ち姿全体を優美な曲線で装飾的に描くのが主流でした。それが時代とともに肉体をともなった現実の女性を意識したものになり、表現も型にはまったものから個性的なものへと変化していきます。このような流れの先にあるのが浮世絵の美人図で、なよやかな町娘から鉄砲肌の遊女、そして恋心や嫉妬に身をやつす心理描写までが描き出された作品へと発展していくのです。江戸絵画における美人図の歴史に、聖なる世界から俗なる世界への変遷が凝縮されているといっても過言ではありません。もちろん、俗っぽいからよくないというのではありません。様式美優先、様式と内容の均衡、そして内容が様式を凌駕するロマン派的な表現、これら全体で豊かな絵画史を形作っているのです。さて、どのあたりがお好みでしょうか。
◆見立の聖と俗
 3 柿本人麿像(部分) |
ところで、美人図や風俗人物図などの中には、「見立」という手法を利用したものがあります。例えば勝川春章の「見立寒山拾得図」は、箒や手紙(詩文)といった小道具と女性を組み合わせることによって、多くはみすぼらしい姿の少年として描かれ、時には怪異な容貌で表現される中国の脱俗の人物である寒山拾得に美女ふたりが見立てられているおもしろさを狙ったものです。いわば古典の力を利用して、作品に奥行きを与え、聖と俗とのギャップによって観る者の興味をひきつける、高等技術と言えるでしょうか。ギャップが大きいほど、効果的かもしれません。
◆洋風画の聖と俗
風俗に対するあくなき好奇心は、西洋の風景や人物を描く際にも発揮されました。桃山時代を中心とした初期洋風画では、西洋からもたらされた図像をもとに、異国の風景や人物が一種理想郷に対するあこがれに似た感覚でとらえられていました。ところが、江戸後期に再び隆盛をみた洋風画では、時には異国の風俗に対する興味が、きわめて俗的な表現をともなって現れることもあったのです。谷鵬紫溟(こくほうしめい)の「唐蘭風俗図屏風」などはその最たるもの。ヤギの頭が乗った料理を前によりそう西洋の男女など、桃山時代の洋風画では考えられない発想です。
そこには、科学的、合理的な世界観を受け入れ、日本も海外も冷静な眼で見つめることのできる精神的土壌がすでに築かれており、この地上には、もはや聖なる世界などどこにもないという意識が働いていると言えば、大げさにすぎるでしょうか。
◆俗物たちの競演
 14 勝絵巻 (部分) |
俗なるものにも程度があります。まったく下品でくだらない低俗なものも時には必要なのが人間の一面でしょう。「勝絵巻」では、男性性器を比べあったり、放屁合戦をしたり、とにかく馬鹿げた競い合いが次々と描かれていきます。しかし描いたのは狩野派の絵師で、おそらく武家が慰みものとして楽しんだ作品と思われます。俗もここまでくると、あっけらかんとした笑いを誘います。
また大坂の廓の日常を描いた「葵氏艶譜(きしえんぷ)」も、何の飾りけもない俗世界ゆえに、かえって人生の悲哀や人間の滑稽さを雄弁に物語ってくれます。このような作品を眺めていると、ひょっとすると、徹底的に俗なる世界を追求した果てには、思いもよらない清らかな聖なる世界が開けるかもしれないなどと、愚にもつかないことを考えてしまいそうです。
(中山喜一朗)