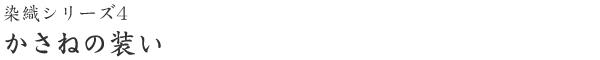No.275
歴史展示室
平成18年3月28日(火)~5月21日(日)
 13.春の景花見の図(部分) 歌川芳藤作 |
右のちょっと後ろを振り返る若い女性は、三枚続錦絵(にしきえ)「春の景花見の図」にあらわされた花見をする美人3人のうちの1人です。画面では桜が満開の水辺をそぞろ歩いています(全図は裏面)。作者は歌川芳藤(うたがわよしふじ)という浮世絵師、刷られたのは弘化4年(1847)~嘉永5年(52)の間ですから、今から160年くらい前の江戸の若い女性のお洒落をつぶさに伝えています。
さて、この女性の姿、現代女性のキモノ姿と似ているようで異なるところがたくさんあります。まず襟元(えりもと)に注目。襟元のあわせはゆるく、襦袢(じゅばん)に掛けた襟が大きくのぞいています。色は紅で絞りの柄が付いています。小袖(こそで)は大振りの菊花を散らした渋い茶色の緑色の縞(しま)柄で、黒い襟を掛けています。時代劇の町娘などによく見られますが、江戸時代の庶民は、普段着の小袖の襟に黒い繻子(しゅす)やビロードの襟を掛けて、髪の油や汚れが小袖に着くことを防いでいました。さて、黒い掛襟の下には、2枚の襟の重なりが見えます。これは、下着の小袖の襟です。「下着」といっても、現代のような「肌着」を意味するのではありません。小袖を重ね着するとき下に着込むほうの小袖を下着というのです。この女性は、薄い青色に巻き貝の柄を染め抜きした下着2枚の上に、表着(おもてぎ)1枚を加えた計3枚の小袖を重ね着しているわけです。しかも全部綿入れ。かつては、綿を入れない袷(あわせ)は初夏と晩秋に用いるもので、冬から春までは綿入れの小袖を1枚から3枚着るのがふつうでした。何枚着るかは寒暖にもよったでしょうが、外出や気の張る場には3枚重ね着するものであり、夏場以外の1枚着というのはかなりラフな格好と見なされていたようです。さて、視線を錦絵に戻しましょう。帯は色違いを2本結んでいるように見えますが、あにはからんや、これは1本の帯。表・裏が別裂(べつぎれ)のリバーシブルの帯は、昼夜帯(ちゅうやおび)といって江戸時代からあり、一部を折り返して両柄を見せるように結ぶ場合もあったようです。ここでは、紅地と緑地に桜と蝶の同柄を染めぬいた昼夜帯です。帯の下では小袖にたるみが見えます。腰からやや下を紐のようなもので括(くく)っています。これは、現代の着付でいう「おはしょり」のようなもの。小袖は、室内では裾(すそ)を引くもので、外に出るときは、襟下をつまんで裾をたくし上げたり、腰の下に紐を結んで裾を上げたりしました。さらに視線をおろしてゆくと、3枚重ねの小袖の裾がめくれて紅色の裾よけがちらりとのぞいています。表着の縞の小袖は、渋い緑色の裏地が付いていますが、裾では表に大きく折り返されて表地に留められています。この折り返し部分をふきといい、江戸時代の小袖では、かなり大きく作るものでした。
江戸時代の若い女性の装いを分解的に見てきましたが、何と言っても小袖を3枚も重ね着しているということに、驚かされることでしょう。しかし、日本の服飾の歴史を顧みると、日本人は「重ね着」ということに特別な意味を見出していたようです。つまり、衣を重ねて着ることは、装いの威儀を正すことだ、という意識の伝統があるのです。その由来はどこにあるのでしょうか。それは、遙か平安時代に成立した宮中の女房装束(にょうぼうしょうぞく)に見出すことができます。いわゆる「十二単(じゅうにひとえ)」と呼ばれる宮中の女性たちの重ね着スタイルは、具体的には、白い小袖に赤い袴(はかま)をはき、まず単(ひとえ)という衣に袖を通してから、その上に何枚も袿(うちぎ)という衣を着けています。これは、平安時代に定まってから、現代の皇室の装束に至るまで、ほとんど変わることなく受け継がれた女性の正装の基本形式で、これ以上の「きちんとした格好」というものは無かったのです。そこから、衣を重ねて着る=礼儀正しい格好をするという意識が生まれてきたと考えられます。
その名残は現代のキモノにも窺うことができます。例えば、振袖(ふりそで)やお祝いの場の略礼装には、半襟(はんえり)とキモノの間に色襟を1枚以上挟みます。これを「重ね襟」あるいは「伊達(だて)襟」といいますが、華やかさを加えるとともに装いの格を上げるはたらきをします。また、結婚式に新郎新婦の親族が着ているような黒留袖(くろとめそで)は、比翼仕立(ひよくじたて)といって、必ず襟、袖、裾の部分は、2枚仕立になっています。これは、黒い紋付きの正装の下には、本来、必ず白い下着を重ねたからで、現代は、着装の便を考えて略式の仕立方をしているわけです。襟元や袖口、裾にちょっとした重なりを作ることは、現代のキモノに残る、平安時代以来の美意識と言うことが出来るのです。
(杉山未菜子)
 13.春の景花見の図(全図) 歌川芳藤作 |