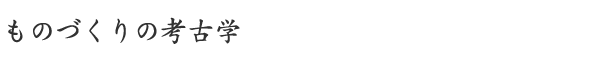No.285
考古・民俗展示室
平成18年8月29日(火)~11月5日(日)
はじめに
弥生(やよい)時代から古墳(こふん)時代前半にかけて、稲作が開始され、国内での青銅器の製作が開始されるなど生業全体にわたる大きな変化が生じていることはよく知られています。その変化を遂(と)げた技術のなかで、当時の人たちは実際にどのような工具を使用してどのような工程で土器や金属器を製作したのかという点に光を当ててみたいと思います。特に今回は土器の製作技法と再生・リサイクルした鉄製品の2つの分野について紹介していきます。
1キレイな土器の作り方―土器に見られる工夫―
 図1、叩き板(大阪・東奈良遺跡・複製) |
土器作りは簡単?難しい? 小さな土器の場合には特別な技術を使用しなくても粘土を指先で捏(こ)ねるだけで目的の形を作ることができます。大きな土器を作る場合、轆轤(ろくろ)がない時代には粘土をひも状にして一段ずつ積み重ねていく「輪積(わづ)み」や「巻き上げ」とよばれる技法を使用しました。土器に粘土の継ぎ目(つぎめ)が残っていたり、接合したときに粘土を押さえつけた指の形が指紋(しもん)までも生々しく残っていたりすることがあります。
縄文(じょうもん)~弥生時代の土器の底部に木の葉の模様が付いていることがあります。これは土器を作るときに木の葉を敷(し)いてその上で土器を作ったためです。粘土を回転させたり持ち上げたりするのを簡単にするための一工夫です。
より薄く、より軽く、より大きく 古墳時代に作られた土師器(はじき)や須恵器(すえき)には、土器の内面や外面に縦方向や横方向の連続した模様や格子(こうし)目文様がついていることがあります。これらの文様は土器の表面を板や棒のようなもので叩(たた)き締(し)めたことで道具に刻まれた文様が土器についたものです。叩き締めることで粘土内に入っている空気を抜き取り、土器をより薄く、大きくすることが可能です。本来は土器を叩くときに板に粘土が付着しないように板の表面に刻み目を入れたものでしたが、次第に刻み目自体が装飾性をもつようになります。
外面を板で叩く時に、内面に当て具とよばれる木製または土製の道具を当てます。古墳時代の須恵器の甕(かめ)には同心円文の刻み目がある当て具でつけられた独特の文様が残っています。
土器もスキンケアは大事 手捏(てづく)ねや輪積(わづ)み・巻き上げの方法で作られた土器は表面の凹凸(おうとつ)が目立ち、全体に粗野(そや)な感じを受けます。この凹凸を板や貝殻(かいがら)、篦(へら)などでなでてならすことが縄文時代の終わり頃以降に一般的になりました。縄文時代晩期から弥生時代前期にかけては、この作業工程は二枚貝の貝殻を使用して行われ、その後、弥生時代前期以降は板材を使用して土器の表面を掻(か)きならしています。このとき刷毛(はけ)で砂の表面を掃いたような文様が残るため、この技法を「ハケ目」といいます。
このハケ目の道具に関する研究を行ったのが、横山浩一氏(1926~2005)です。氏は実際に樹種(じゅしゅ)、木取(きど)りを様々に変えた板で粘土をなでて表面を観察し、実際の土器と比較しています。その結果、ハケ目の平行線は板の木目(もくめ)が土器の表面になでつけられた結果生じたものであると指摘(してき)しています。また、その後横山氏の指摘に近い形で実際にハケ目の道具が出土していますが、ただの板きれと間違えそうな遺物(いぶつ)の正体や使用方法が明らかになったのは横山氏の研究に負うところが大きいのです。
生焼け厳禁。中までしっかり火を通す 福岡市東区の唐原(とうのはる)遺跡で土器を焼いたとみられる土坑(どこう)が約300基確認されています。この状況に似た土器の焼成技術(しょうせいぎじゅつ)が中国・雲南(うんなん)地方にあります。木の枝を敷いた上に土器を置き、全体をわらで覆(おお)い、上から粘土をかぶせて内部に点火して一昼夜焼き続けるという、一般に「覆い焼き」とよばれる焼き方です。この方法で土器を焼成したときには土器の表面に黒色の大きな斑点(はんてん)が生じることが多く、この黒斑(こくはん)の位置から土器を焼くときに土器をどう置いたかを推定することができます。
このような様々な技術を使いながら、端正(たんせい)な形の弥生土器が作られています。実際に土器を見ながら紹介した技術がどのように使われているか、さがしてみませんか。