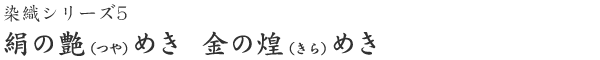No.315
美術・工芸展示室
平成20年3月18日(火)~5月18日(日)
 |
| 4 檜垣山吹文様小袖 |
右は、江戸時代、寛文期(1661~72)以降元禄期(1688~1704)までの間に仕立てられたと考えられる小袖(こそで)です。文様は檜垣(ひがき)と色とりどりの山吹。まず、絞(しぼり)によって、文様を施す部分を防染(ぼうせん)し、地の部分を黄色に染めます。白く残った部分には、ふたたび絞により山吹の紫や葉っぱの浅葱(あさぎ)や萌葱(もえぎ)を染め、鹿子絞(かのこしぼり)ふうの型染(かたぞめ)で檜垣と山吹の一部に紺と薄紅(現在はほとんど褪色)を加え、さらに金糸や色糸で、山吹全体や、葉や花びら、檜垣の竹骨の輪郭を繍取(ぬいとり)します。左右に大きく振られた檜垣にこぼれ落ちるような山吹をあしらった意匠は、動きに富み、今見てもなかなか斬新です。
さて、この小袖の華やかな印象をもたらしているのは、意匠の巧みさばかりではありません。地紋(じもん)が織り出され、ツヤツヤとした光沢を放つ絹地の風合いもまた、注目すべきところです。この小袖の生地(きじ)は綸子(りんず)といい、現在でも、振袖(ふりそで)などのフォーマルなきものに、よく見られます。
綸子という絹織物は、中国で考え出され、 明時代、盛んに織られるようになりました。日本では、江戸時代中頃まで長崎を窓口にして、生糸(きいと)とともに綸子の反物(たんもの)が、膨大な量、輸入されていました。その始まりがいつ頃かは判然としませんが、上杉謙信(1530~78)所用と伝わる胴服(どうぶく)(羽織のような上着)の中に綸子を用いたものがあり、これが、一番古い使用例だとされています。
綸子は、輸入開始からそう時を経ずして、小袖、とくに女性の小袖生地として、急速に需要を伸ばします。なぜなら、光沢や肌触りのなめらかさ、地厚(じあつ)さ、しなやかさが、ほかの絹織物に比べて格段に優れていたからです。時期はやや下りますが、慶安3年(1650)の『女鏡秘伝書(おんなかがみひでんしょ)』という書物でも、小袖生地として「綸子はしなやかに、しかも光有りて、一入(ひとしお)良きものなり。第一、皺(しわ)よらざるものなり。」と、綸子をイチ押ししています。そして、綸子の広まりと軌を一にするように、小袖の意匠にも大きな変化が起こりました。複雑な絵羽(えば)文様(縫い目をまたがる文様)が見られるようになったのです。
綸子に先だって、華やかな色柄の小袖を仕立てるのに多く用いられていたのは、練緯(ねりぬき)という絹織物です。耳慣れない名前ですが、経に生糸、緯に精練した糸を用いることに由来します。この練緯も美しい光沢のある白生地です。ただ、経糸の浮きが長い繻子織(しゅすおり)の綸子に比べて、平織(ひらおり)で経緯の交叉点の密度が高い練緯の輝きというのは、乾いて粉をふいたような感じがします。さて、練緯全盛期の小袖意匠は、どうも、反物幅ベースで考えていたふしがあります。今残っている桃山時代の練緯による小袖の意匠は、ごくわずかな例外を除き、飛び文様のもの、背縫いをはさんで左右対称をなすよう文様が配されるもの、片身替(かたみがわり)といって左右の身頃(みごろ)の地色や文様が全く異なるものに大別されます。縫い目を不規則にまたがる文様は、非常に部分的にしか見られません。
 |
| 5 透垣竹梅文様小袖 |
ところが、綸子が生地として盛んに用いられるようになると、最初に見た小袖と同じような、左右の対称性を大きく崩し、かつ、文様があらゆる縫い目をまたがって一つながりになったものが登場します。つまり、小袖全体を一枚の画面に見立て、そこに自由に絵を描くように文様をあらわすようになるのです。このような文様意匠は、仮絵羽(かりえば)という工程を踏むことが必要です。最初に見た小袖でいうと、まず、白綸子の反物を裁(た)ち、小袖の形に仮仕立(かりじたて)をしてから、檜垣や山吹の絵柄を描き込んだのち、仮仕立をほどいて、地染(じぞめ)、絞染(しぼりぞめ)、型染、刺繍の加工を施しています。
絵羽文様は、原理から言えば、練緯でも綸子でも可能です。仮絵羽の工程は、練緯の小袖においても取り入れられていたはずです。しかし、作業のしやすさ、仕上がりの良さの点で、綸子は、まったくもって画期的でした。シャリっとした感触の練緯は皺になりやすく、生地を複雑に染め分けるために絞を繰り返すのには具合がよくないのです。また、染も、繊維表面の膠質(にかわしつ)がよく取り除かれた綸子のほうが、深みのある冴えた色合いに上がります。実に、綸子という、皺にならない、発色の良い新素材を得ることで、小袖の意匠は飛躍的に自由度を増し、絵画的な文様の発展が方向付けられたと言えましょう。
綸子の特質を生かすことで促された小袖の意匠展開が、行き着くところまで行った感を呈するのが、徳川秀忠の娘で、後水尾(ごみずのお)天皇の中宮(ちゅうぐう)となった東福門院(とうふくもんいん)和子が誂(あつら)えたお召し物です。ご愛顧の呉服商に伝わった注文台帳をめくれば、極上の綸子をコントラスト鮮やかに染め分け、鹿子絞や金糸繍(きんしぬい)を駆使して、菊花、水流、棕櫚(しゅろ)の葉といった多彩なモチーフをでかでかと配置する大胆なデザイン画が、次から次へと、目に入ってきます。
 |
| 2 枝垂桜鳳凰尾長鶏文様舞衣 |
さて、東福門院が72歳で歿するのが延宝6年(1678)。折しも、その頃より、流行の最先端を行くセレブな女性たちの間では、綸子に金糸繍の、これでもかと言わんばかりの光彩を放つ小袖は、野暮ったく感じられてきたようです。ちょうど、繊細な暈(ぼ)かしが目新しい友禅染(ゆうぜんぞめ)が知られるようになると、生地の好みも、滑らかな綸子から、表面に細かいシボのよった縮緬(ちりめん)へ、またたく間に移りかわり、軽妙で華やかな元禄の世を迎えることになったのです。
(杉山未菜子)