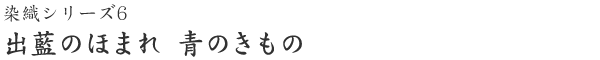No.322
歴史展示室
平成20年7月15日(火)~9月15日(月・祝)
 |
| 1 帷子 麻地 雪の下文様 江戸時代 |
藍(あい)は、日本人にとって最も馴染み深い染料で、蓼藍(たであい)をいう植物から取れるものです。「青は藍より出でて藍より青し」と言いますが、藍からは、さまざまに表情の異なる青色が染め出され、「藍」、「縹(はなだ)」、「浅葱(あさぎ)」、「千草(ちぐさ)」、「紺」など、さまざまな名前で呼び表されてきました。明治8年(1875)、化学の教師として来日した英国人アトキンソンは、日本人の生活のすみずみまで藍の染めものが行き渡っていることに強い印象を受け、藍の色を「ジャパン・ブルー」と呼んでいます。また、明治23年に来日したラフカディオ・ハーン(小泉八雲)も「青い屋根の下の家も小さく、青い暖簾(のれん)をさげた店も小さく、青いきものを着て笑っている人も小さいのだった」という感想を書きとめています。この展示では、藍主体の染めが施された江戸時代の衣料を集め、藍から出(い)づる青の多彩な美しさを紹介します。
◆夏の藍染め
ゆかたを着ての花火見物や夕涼みは、夏の楽しみの1つです。最近のゆかたは街着としても着られるよう、生地の種類やデザインも豊富で、帯揚(おびあげ)をつけたり帯留(おびどめ)をしたりと、着こなしも多様になっています。とは言え、昔ながらの白地に紺、あるいは紺地に白の染抜(そめぬき)文様が施されたゆかたの清々しい雰囲気は、格別です。
「ゆかた」という語は、「湯帷子(ゆかたびら)」に由来すると言われています。帷子とは麻の単(ひとえ)のきもののことで、主として身分の高い人が風呂(古くはサウナのような蒸し風呂)に入るときに身にまとっていた白い帷子を湯帷子といっていました。湯帷子は、のちに、湯上がりに汗取りのためにバスローブのように体にひっかけるものも言うようになり、「手拭(てぬぐ)い」に対して「身拭(みぬぐ)い」とも呼ばれました。江戸時代、木綿(もめん)が庶民の間に広がると、木綿の身拭いが重宝され、また、バスローブのみならず、夏のくつろぎ着や、旅装、レインコートとしても用いられるようになり、今日のゆかたと同じような性格を持つに至ったのです。
ゆかたには、もっぱら藍の型染(かたぞめ)で文様がつけられました。それは、もともと木綿が藍や茶以外の染料に染まりにくいこともありますが、何より藍から得られる様々なブルーがもたらす清涼感が夏の衣料にぴったりだとされたからでしょう。ゆかたに用いる型染は、中形(ちゅうがた)といって、小紋(こもん)より大柄のパターン文様を切りぬいた型紙を用いて木綿表面に糊(のり)を置き、藍の染液につけ込みました。糊置(のりおき)部分が白く抜けて文様になるわけですが、型がずれないように表裏2度にわたり糊置する手間をかけ、藍と白のコントラストをくっきり染め出すことが好まれました。
 |
| 8 錦絵「四条河原夕涼之図」歌川国貞作 |
 |
| 14 被衣 麻地 菊大紋裾梅散 |
◆慶(よろこ)びの藍染め
ゆかたは、江戸時代から現在に至るまで、活き活きと命脈を保っている伝統の装いですが、いっぽう、全く廃(すた)れてしまった装いの1つに「かつぎ」を挙げることが出来ます。「かつぎ」もまた、もっぱら藍染(あいぞめ)が用いられる衣です。「かつぎ」とは、被衣とも書き、女性が外出時に衣服を頭から被ること、また、その衣のことを指します。平安時代に公家(くげ)の女房(にょうぼう)の間から始まり、江戸時代には庶民の女性の間にも広まるとともに、独特の仕立(したて)方や意匠が生まれました。仕立方は、ふつう肩山(かたやま)の高さにつける襟肩(えりかた)あきを10センチ以上も前身頃(みごろ)側に下げており、袖(そで)をとおすことなく頭から被りやすい形になっています。
意匠は、大きく3つに分かれます。1つは、肩と腰下は濃紺の無地で、間に白地を設け、濃い青と薄い青の松皮菱(まつかわびし)の横縞をつらぬき、その中に花の丸や菱形の文様を散らすもので、「御所被衣(ごしょかつぎ)」と呼ばれます。もう1つは、ちょうど御所被衣の横縞部分を、風景文様などに置き換えたもので、「町被衣(まちかつぎ)」と呼ばれます。3つ目は、頭にあたる部分に濃紺の菊や梅の大紋(だいもん)、身頃には多種多様の型染文様、裾(すそ)に濃紺の区画を配するもので、「大紋被衣(だいもんかつぎ)」と言います。天明(てんめい)元年(1781)頃に著された『見た京物語』に「御所の被はだんだら筋、町はもようなり」と書かれており、通称どおり、御所被衣は公家そして武家の女性、町被衣、大紋被衣は町方の女性が用いたものと考えられます。あるいは、使用者の身分が判っている遺品から、それほど厳格な違いではなかったと判断するむきもあります。
 |
| 20 被衣 麻地 菱大紋裾松皮菱(部分) |
被衣は、江戸では、万治(まんじ)年間(1658~61)に廃れていたと言われますが、上方(かみがた)では江戸時代を通じて行われました。また、地方にも伝わり、とくに大紋被衣は、花嫁が嫁入りの際に被る婚礼衣裳として誂(あつら)えられるようになりました。それゆえ、染めの型紙をさかんに切り替えて華やかさを出し、また、松竹梅などの吉祥(きっしょう)文様が好んで用いられています。
(杉山未菜子)