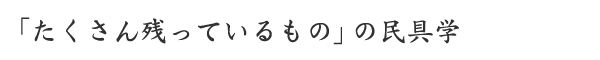No.486
企画展示室4
平成29年1月24日(火)~平成29年4月9日(日)
2 千歯扱〈せんばこき〉

千歯扱
千歯扱は、稲や麦などの穀類を穂からはずすための道具です。ひと目みてわかるように、髪をとく櫛のような形をした鉄の歯が並んでいるのが大きな特徴です。歯と歯のすき間に、実った稲束を差し込んで引っ張ると、籾がバラバラと下に落ちていきます。
鉄歯の千歯扱は、元禄(げんろく)元(1688)年に大坂で発明されたといわれています。しかし、福岡の農学者・宮崎安貞(みやざきやすさだ)(1623-97)の著書『農業全書』(1697)に、この新しい農具のことは記されておらず、各地へと広まっていったのは、もう少し後のようです。
それまでの脱穀は、稲穂を1本ずつ扱箸(こきはし)という棒で挟みしごいていましたので、千歯扱が登場したことで作業能率は飛躍的に高まり(3倍とも10倍ともいわれます)、当時の農業の進歩に画期的な役割を果たすことになりました。
千歯扱には大きく分けて稲扱(いねこき)と麦扱(むぎこき)の2種があります。稲扱のほうが歯と歯の間隔が狭く、稲穂の籾を一粒一粒扱き落とせるよう調整されています。いっぽう麦扱のほうは、麦の茎と穂を切り離すのが役目でしたから、歯の間隔は比較的広めにつくられました。
千歯扱はかつて、農家が現金をやりくりして購入し、補修しながら大切に使い続けた農機具でした。それが姿を消したのは、大正時代に全国の農家で回転式足踏脱穀機が使われるようになったためです。その転換は短期間に起きたようで、昭和になると使われなくなった千歯扱が農家の納屋にしまわれたままになりました。戦後になって数多くの千歯扱が収集されたのも、そんな理由がありました。
3 唐箕〈とうみ〉

唐箕
昔の農機具といえば、唐箕を思い浮かべるという人は多いのではないでしょうか。その大きく個性的な姿は、民俗資料館には欠かせません。
唐箕は、把手(とって)を回して起こした風の力を利用して、穀物にまじった藁屑(わらくず)や籾殻(もみがら)などを吹き飛ばし、実のつまった重い穀粒を選びとるための道具です。中国で生まれたとされる唐箕が、日本で使われ始めたのは、ちょうど千歯扱が発明されたのと同じ元禄年間(1688-1704)頃、広く普及したのが天明(てんめい)~寛政(かんせい)年間(1781-1801)頃ではないかと考えられています。
それまで穀物は箕(み)(後には唐箕に対して手箕(てみ)とも)とよばれる、大きな笊(ざる)のような形をした、それでいて浅く、目のつまった道具を使って選別していました。風の吹くところで箕に入れた穀物をあおり、塵(ちり)や屑を飛ばしたのです。それが唐箕を使うと、機械の起こす風の力で、いつでも楽に作業ができるようになりました。しかし、千歯扱が扱箸に取って代わったのと違い、箕が消えてしまうことはありませんでした。少量の選別ならば、わざわざ大きな唐箕を引っ張り出すことはなかったからです。
唐箕があまり使われなくなり始めたのは戦後になってからのことでした。高度経済成長期に農業の機械化が進み、耕耘機や稲刈機が普及するとともに自動脱穀機が登場します。そこには脱穀だけでなく唐箕の風選機能も組み込まれていました。さらにコンバインの普及も進み、唐箕はその役目を終えたのです。
今でもまだ、納屋の隅で埃(ほこり)をかぶった唐箕を見かけることがあります。他のこまごました道具類は整理できても、なかなか唐箕は捨てられないという話もよく聞きました。その理由は、単純に大きすぎて捨てづらいということだけではないでしょう。取っ手を回す感触、明るい日差し、舞いあがる埃と稲の匂い。唐箕には、そうしたかつての農作業の思い出が染み込んでいて、どうも捨てるに忍びない。そんな風にも見えるのです。