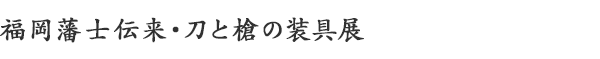No.528
企画展示室1
平成30年12月26日(水)~平成31年2月24日(日)

螺鈿柄籠槍・大身槍・薙刀
はじめに
刀は「武士の魂(たましい)」、槍は「一番槍(いちばんやり)」といわれ、武士にとって大切なものですが、実際に使われる時には、刀は柄(つか)や鍔(つば)、鞘(さや)といった拵(こしらえ)、槍は鞘や柄など、様々な装具が付けられました。この展示では本館収蔵の福岡藩士伝来の刀と槍を中心にして、刀剣をめぐる福岡藩の武家の歴史や文化を紹介します。
藩士肖像の中の刀装具
室町から戦国時代には、徒歩(とほ)・多人数での合戦が多くなり、武士には太刀(たち)よりも短く、切り合いに有利な打刀(うちかたな)が広まります。打刀はふつう刃を上にして腰の帯(おび)に差します。もっとも天下統一の時代に活躍した福岡藩の重臣達の肖像には、合戦で軍勢(ぐんぜい)の指揮を執る上級武士が、実戦的に打刀を頑丈(がんじょう)な陣太刀(じんだち)作りの拵で、太刀のように腰に吊(つ)るしたり、刃を上にして帯に差す姿が見られます。
江戸時代前期、17世紀後半の福岡藩家老の肖像では、平服(へいふく)のラフな姿でくつろぐ横に、豪華な鞘を持った自慢の大刀(だいとう)がおかれ、細かな装飾で飾られた短刀(たんとう)を身に着けて描かれています。また大刀が刀掛(かたなかけ)に置かれ、大胆な柄と鍔(つば)だけで示されている肖像もあります。しかし18世紀に入ると、地味で短めの差料(さしりょう)の刀を刀掛に置き、揃いの脇差(わきざし)を身に帯びた姿が多くなり、公的に裃(かみしも)を着た場合も、くつろいだ羽織姿(はおりすがた)でも、揃(そろ)った打刀大小が必須(ひっす)のアイテムで描かれました。
打刀の拵、大小の拵
江戸時代の福岡藩には、戦国~安土・桃山時代の由緒(ゆいしょ)を伝える大刀を持つ武士もおり、古風な太刀拵(たちこしらえ)、人目を引く派手な鍔付の大刀拵が残されています。江戸時代初めは、武士は自分に合った長さや反りの違う刀を持っていたため、それらの拵も、個人個人で長さや形状が異なる場合が多かったとされます。
しかし江戸時代前期の17世紀中頃から、武士の刀の長さは、幕府や藩で基準は異なりますが、刀で2尺(しゃく)2、3寸(すん)程度(約66~70㎝)、脇差は1尺5寸(約45㎝)程度が一般的になり、反りも太刀に比べて小さい直線的な刀になりました。これらの特徴をもつ刀が多く作られ「新刀(しんとう)」と呼ばれました。
江戸時代に中心となった刀と脇差のための大小の拵は、同色や同系統の色で巻いた柄に、似たデザインの鍔で、鞘は黒蝋(ろう)色塗(ぬり)と呼ばれ黒漆塗(くろうるしぬり)で揃えられました。揃えの大小二本(だいしょうにほん)の拵を、公的にも私的にも差して過ごすことが武士の証(あかし)となりました。また形状が同じ大小は大名家や武家の儀式、行列などで、家中全体が揃って統一した美観を生み出すことにもなり、江戸時代の武家のファッションになりました。また大小の刀や拵の長さ、造りに適した、竹刀剣術や、居合(いあい)、抜刀(ばっとう)術も盛んになりました。そして幕末から維新期、武士や浪士が、刀で激しく切り合って戦う下地はこうした社会から生まれたとされます。
脇差と短刀の拵
脇差は、打刀の大刀に添えて差されるもので、刀にちかい2尺以上の長さでも、添えに差すものは大脇差(おおわきざし)と呼ばれました。長さの区分では、中脇差、短刀に近い小脇差などがあります。江戸時代中頃からは、刀より20㎝は短い中脇差が、一般に「脇差」とされ、刀と揃いの拵で差されることが多くなりました。
短刀は、長さ1尺(約30㎝)程度の細身で鋭利なもので、古来、合戦で甲冑を着た武士が組打(くみう)ちした時に、鎧兜の隙間から相手を刺すために使われ、「鎧通(よろいとおし)」ともいわれます。握りや扱いの邪魔にならないよう、鍔も小さめか、目立たない合口といわれる拵に収められました。短刀より長めでがっしりしたものは腰刀(こしがたな)といわれ、脇差の代わりにもなりました。短刀や腰刀は組打で素早く抜くため、刃を下に向け帯に差すこともありました。
江戸の平和な時代には、短刀や脇差は武士が自分の屋敷内でくつろぐ際や、お忍びで外出する際に一本だけ差すこともあり、意匠(いしょう)など趣味的に凝ったものも作られました。また武家の女子に守り刀として与えられるのも短刀でした。
刀装具あれこれ
刀装具の柄(つか)、鍔、鞘には様々な金具が付属しています。柄先の柄頭(つかかしら)、刀身を柄に止める目釘を隠す目貫(めぬき)、鍔を固定する切羽(せっぱ)、縁(ふち)、刀身を鞘に固定する鯉口(こいぐち)、鞘先のコジリなどさまざまに細工された金具がつきます。ほかに鞘に付ける小刀、笄(こうがい)などは目貫と合わせ三所物とされます。また鞘に緒を通す栗形(くりかた)や、下げ緒や緒を帯に止める返角も付きました。
大きさや規格の似た大小拵が増え、城中や殿中用として、地味な金具が付けられた拵もありますが、その一方で柄や鞘、鍔や様々な金具の部分で、材料、細工、デザインに凝ったものも作られ、大名や上級の武士は豪華な作りの拵も持ちました。一般の武士も、装具の一部だけに金銀の細工を施したり、赤銅(しゃくどう)、鉄の普通の材料でも凝った細工にするなど、熱意は大変なものだったといわれます。
江戸時代の刀の拵は、江戸時代の中後期から出回る金銀銅の豊かな材料や、鞘師(さやし)、塗師(ぬりし)、柄巻師(つかまきし)、白銀師(しろがねし)など刀装具の職人の精巧で創造的な技術によって、美術的な工芸品になって行きました。