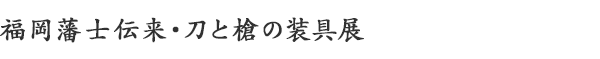No.528
企画展示室1
平成30年12月26日(水)~平成31年2月24日(日)
福岡藩の刀工とその作品
福岡藩の武士たちの拵の中に収められた新刀を作る刀工(とうこう)には、城下町の信国(のぶくに)派と石堂(いしどう)派の2つがありました。信国派は、もと京都の刀工で室町時代に豊後(ぶんご)に移り栄えました。1600年黒田長政(くろだながまさ)が筑前へ入国した際に、信国吉貞(よしさだ)が福岡へ招かれ、数年後に苦労して城下町に移ってきました。幅と厚みのある実戦的な刀を作ることで有名で、また長政が考案した袋鑓(ふくろやり)を作製したのもこの信国です。一門が城下などに工房を構え、江戸時代の中期、享保(きょうほう)時代には、信国重包(しげかね)(のち正包(まさかね)と改名)が、将軍徳川吉宗(とくがわよしむね)の開いた全国の新刀コンクールで一番の成績を収め、以後、「茎」(なかご)に一枚の葵の葉を刻むことを許されるほどでした。
石堂派は、備前福岡(現岡山県)の一文字派の流れで、やはり長政の筑前入国の際に城下町福岡に招かれた是次(これつぐ)を祖とし、それを継いだ守次などの名人が出ました。工房を箱崎(はこざき)に持ち、新刀のなかでも反りのある上品で華やかな刀を作製しました。福岡藩の刀工の作品は、藩内での刀剣の需要を満たすことが中心で、あまり他国に出回らなかったため、信国重包のほかは明治まであまり全国でしられることが少なかったといわれています。なお江戸時代の初めには東国から下坂(しもさか)氏が二代藩主忠之の好みで脇差などを作製しています。
槍の装具
槍は室町時代から戦国時代に、合戦で武士が最も頼りにした柄付(えつき)の武器です。馬乗や徒歩で戦う武士の槍は、足軽の長柄(ながえ)と区別して、「持槍(もちやり)」といわれ、さらに短い室内戦専用の「手槍」もありました。
槍の先には剣状の穂先(「鎗身(やりみ)」)があり、穂から伸びる細長い「なかご」(茎)を、木製の柄の中に押し込んで目釘で止め、その上を弦(つる)などで巻き漆をかけて丈夫にし、槍や刀と打ち合う部分を造りました。穂先は通常15~20㎝前後で、南北朝時代(なんぼくちょうじだい)終わりの短刀の形から、刺突(しとつ)に適した直線状の直鑓(すぐやり)が一般的となりました。形も剣形だけでなく、細い柳の葉の形や、笹の葉に似て中間の膨らんだ形も出現し、穂の片側に突起状の鎌のある片鎌鑓(かたかまやり)、突起が左右に出た十文字鑓(じゅうもんじやり)も作られました。穂先も、平たい刀や剣と違い、断面が二等辺三角形や正三角形、菱形(ひしがた)など、突きに強く折れにくい形になりました。なお1尺(約30.3㎝)以上の長大な穂先は大身鎗(おおみやり)といわれました。
穂先を収める槍の鞘は、通常は直鑓用で剣の鞘状ですが、片鎌槍や十文字鑓用では、基部(きぶ)が幅広のものがあります。ただ鞘は穂先の形に関係なく、円柱や多角柱、熨斗(のし)などの奇妙な意匠(いしょう)のもの、獣毛(じゅうもう)、羽毛(とりけ)で飾ったものなど、形や大きさもさまざまに作ることができました。
持槍の柄(え)は両手で扱いやすい2間(約3.6m)までの長さです。主に樫(かし)の木を材料とし、表面に何も塗らない白木造(しらきづくり)が一般的ですが、黒漆や朱(しゅ)漆を塗ったものもあります。芯(しん)の木材に寄木や竹を張り合わせ、長さや強度を増したものや、柄の全体や一部に螺鈿(らでん)を施し装飾化した豪華(ごうか)なものもあります。柄の下には石突(いしづき)と呼ばれる突起状の金属部が付けられて柄元を保護し、また穂と石突両方で戦いに使えました。

打刀を差す福岡藩士たち
合戦がほとんどなかった江戸時代、槍の鞘や柄は、大名の武威や藩士の武功を示す象徴となり、とくに鞘は家の印(しるし)とされました。藩内でも武士の先祖の武功、家の上下関係や所属を示す証で、上級武士は馬に乗る身分はもちろん、徒歩でも家の自慢の槍を、槍持の中間(ちゅうげん)に担(かつ)がせて外出し、また公用の旅行でも携えました。その大規模なものが「下に下に」と進む大名行列で、大名家の槍は遠くからも見えました。また槍は普段、屋敷の長押(なげし)に何本も掛けられ、来客に家の武功も誇るとともに、いざという時の頼りになる実戦武器でした。 (又野誠)