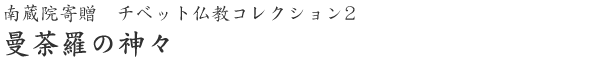No.420
企画展示室3
平成25年10月8日(火)~
チベット仏教の神髄と言えるものが曼荼羅![]() です。曼荼羅は古いインドの言葉で「本質を有するもの」と訳され、本来は円のように完全な境地、あるいは多くの神仏が集う神聖な場所を意味していました。このような曼荼羅を形としてあらわそうとした時、その原形となったのは古代インドの人々が世界の中心にあると信じた聖なる山、須弥山(しゅみせん)(スメール山)でした。
です。曼荼羅は古いインドの言葉で「本質を有するもの」と訳され、本来は円のように完全な境地、あるいは多くの神仏が集う神聖な場所を意味していました。このような曼荼羅を形としてあらわそうとした時、その原形となったのは古代インドの人々が世界の中心にあると信じた聖なる山、須弥山(しゅみせん)(スメール山)でした。
須弥山図(No.12・図1)はこれをあらわした掛軸で、海水をたたえた円盤の中央には巨大な須弥山がそびえ立ち、山の中腹には東西南北を護る四天王の居城、頂上には帝釈天(たいしゃくてん)の宮殿が描かれています。また海の四方には私たちの住む大陸や島も描かれています。
平面として描かれた曼荼羅は、このような須弥山を真上から見たイメージをもとにしています。中心には曼荼羅の主尊が宮殿の中にあらわされ、その周囲を多くの神仏が取り巻いています。これらの神仏は私たちの肉体や精神を構成するさまざまな要素を象徴しているとされ、それらが中心となる仏のもとに関係し合い、いわばひとつの組織や世界として機能している様子をあらわしているのです。
曼荼羅は本来は神仏が宿る場として地面に描かれ、祈りが終わるとすぐに壊されるものでした。臨時に用いられる法要用曼荼羅(No.14)も、そうした伝統を汲んでいます。しかし仏教が発達するにしたがって紙や布に描かれ、何度も用いられるようになります。また徐々に神仏の姿や配置も整理され、やがて日本では金剛界(こんごうかい)・胎蔵界(たいぞうかい)の両界曼荼羅図(参考図)へと発展していきました。
ところで今回展示した立体曼荼羅(No.13・図2)は文字どおり曼荼羅を立体的にあらわしたもので、チベット仏教ニンマ派の教義にもとづいてネパールで制作されました。外周の円は火炎が燃えさかる山脈、その内側は八つの墓場で死骸や悪鬼があらわされています。さらにその内側には巨大な宮殿が建ち、中には法身普賢(ほっしんふげん)(クンツ・サンポ)を中心として周囲を寂静(じゃくじょう)・憤怒(ふんぬ)の百尊が取り巻いています。
寂静・憤怒の百尊は「中陰聴聞解脱(ちゅういんちょうもんげだつ)」(いわゆる「死者の書」)という経典に登場し、死者の魂が次に生まれ変わるまでの間に出会うと説かれる神仏です。チベット僧は死者の枕元でこうした情景を語り、その魂がより良い再生を遂げるように祈ります。またチベットの仏教徒もこうした情景をあらわした曼荼羅を日常的に見ることで仏の世界を思い浮かべ、また自身の来世における幸福を願うのです。
(末吉武史)
 |
| 図2 立体曼荼羅 |